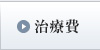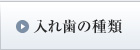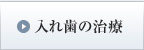口臭
2016.2.27
大阪府東大阪市 大阪入れ歯・義歯 歯科助手の前川です。
今回は口臭の原因や症状のお話をします。口臭の原因は生理的口臭、病的口臭等があります。生理的口臭とは、普段の食事や生活の影響で起きるものです。たとえば、喫煙や飲酒をしたときに「息が臭くなる。」のも生理的口臭です。ほかに、焼き肉や韓国料理などニンニクが入っている料理を食べると、翌日まで息が臭くなります。でも、これらは時間が経てば自然と消えてしまうものです。また、昼間はほとんど口臭がしていない人でも、朝起きたときには口が臭くなります。そして、誰でも緊張すると口が乾くために口臭がします。その他、お腹がすく時間帯や疲れた時にも唾液が減少するため、口臭が強くなりやすいです。これらが、一般的な生理的口臭です。
生理的口臭なお口の中を清潔に保つことによって改善されます。目覚めの口臭は、口の中の細菌や汚れ、唾液量によって変化します。朝を迎えるためにも日々のケアが大切です。まずは、細菌の増殖が始まる直前、寝る前に歯を磨くことで歯垢や汚れを取り除き、ニオイのもととなる細菌を減らすことが重要なカギとなります。死んだ細菌や新陳代謝ではがれた粘膜上皮の細胞などからできた舌苔が舌に付着していると口臭の原因となります。
1日に1回、起床直後に舌ブラシや軟らかい歯ブラシで舌を磨きましょう。強いストレスを感じるときは、睡眠中のように唾液の分泌が減ってしまいます。口の中の生理機能に関連する自律神経系の働きを整えるために、生活習慣を規則正しくし、バランスの良い食生活をおくることが不可欠です。当院では口臭測定器もございますのでお気軽にお声かけ下さい。
大阪入れ歯義歯へ
カテゴリー:お知らせ /コメントはまだありません

![[診療時間] 平日 9時~12時 / 14時~19時、土曜 9時~12時 / 14時~18時、休診日:日曜・祝祭日](../img/common/head_info.jpg)
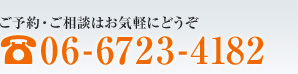


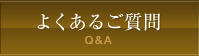



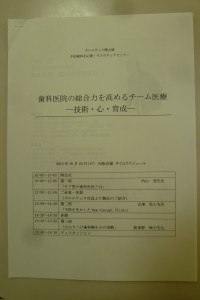

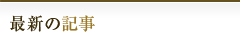
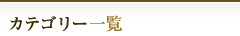


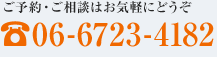
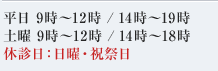
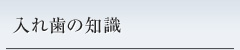
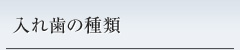
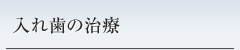



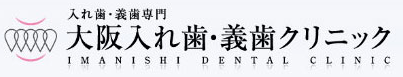
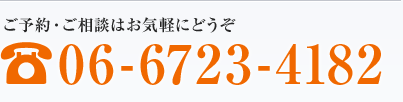
![[診療時間] 平日 9時~12時 / 14時~19時、土曜 9時~12時 / 14時~18時、休診日:日曜・祝祭日](../img/common/footer_info.gif)